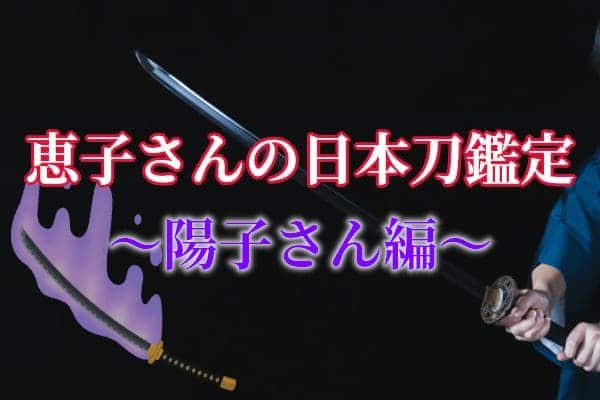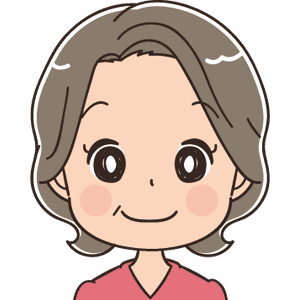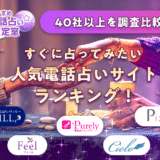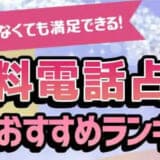執筆者:
ゆい現役イタコの恵子さんと陽子さんはたまにタッグを組んでお仕事をなさってます。
恵子さんは祓う力が強く、陽子さんは縁をつないだり切ったりする力が強いイタコです。
今回はそのお二人の日本刀の除霊の現場に立ち会わせていただきました。
室町時代の日本刀
日本刀は奈良時代から作られたとされ、鎌倉時代にその形を固定したといわれています。
日本刀ができるまでは大陸から来た直刀がベースであり、独特の沿った形は武士の台頭とともに出来上がったとされています。
鎌倉後期から室町時代に入るころ、日本刀は量産まではいきませんが武士や僧侶に行きわたりはじめ日常に入るようになりました。
今回はお祓いの現場に立ち会わせていただけるということで。しかも、恵子さんと陽子さんのお二人のタッグということで
お久しぶり。元気だったかしら?少し体調悪くしたのね、大変だったわね
全く会話をしなくても会話が進むというこの現象をどのように伝えればいいのか
まあ、今回はこれをやるからなんだけどもね(日本刀を包みから取り出す)
あなたこういうの好きだったかと思ってね。私は刀だなってくらいしかわからないんだけども。刀もなんかいろいろと種類があるんでしょ?
ですねえ。大まかに太刀か脇差だとは思いますが……大太刀とかあのへんはいわゆる御神刀とかでしょうし。守り刀だと短刀とか……そこそこ大きな奴を嫁入りに持って行って摺りなおして薙刀にしたものとかもあるらしいですけども
頑張って盛り上げます。それで、これはどっからきたんですか?
年代物っていうことで古物商から購入した人がいてね。ちゃんとした資格も持ってるお店からの購入だから何かの問題があるという程ではなかったのよ。ただ、説明としては実戦で使われてたものなので人を斬っている可能性もあります、ということだったのよね
そうなのよね。購入したその日から家の中にいろんなものが出るようになったので、三人くらい経由して私のところに来たんだけども
それで軽く解いたらよくわからないくらいに濁ってるのよ
陽子さんと恵子さんのタッグ
恵子さんと陽子さんは同じイタコであっても得意分野の違う二人になります。
恵子さんが祓うことに特化しているなら陽子さんは払ったものを本来のものに戻す縁を作る力が強いといった感じです。
並んでいると一見すればご婦人二人にしか見えない二人ですが、イタコとしての現場に立ちあうと、いかに二人が特殊なのかがわかります。
何か絡まっている感じよね、表面に。こう、被膜というか邪悪な被膜というか
元の観賞用の刀に戻して、あげたいんだけどもこれたぶん、守護用のでしょ?
守護用の刀って本来は守護してる存在がそれなりに残ってるんだけども、この刀にはそれがないのよね。だから、私の考えとしてはまず本来の持ち主を特定してなんで守護刀にしたのか。守護していた存在をもう一度これにおろして今の持ち主に戻したいのよ
できればなるはやってやつで終わらせたいのよ。それで、持ち主の特定をあなたにも手伝ってほしくて。ほら、歴史とか好きでしょ?
好きですけども、大河ドラマとか日本史とかのレベルですよ
これは逃げられないパターンですね。わかります。ただ、漠然とこの時代って言われても日本全部って考えるとかなり無茶がありますよ
ある程度は絞るわ。そこからまず最初の持ち主を見付けて降霊させてしまおうかと
そっちのほうがいいんじゃないですかね?整理すると……
・刀の最初の持ち主を特定する
・本来の守護刀にするために、現在の不要な何かを外す。
・購入した人に、守護刀になったものを渡す
で、購入した人との縁を陽子さんが作る。守護刀に戻した際に、本来の霊的なお守りになっているものと刀の縁をしっかりと陽子さんが結ぶ。ってことですよね?
聞いててよくわからない部分をメモにして相関図作ってました。持ち主の特定が大変な気がしますねえ
この刀実際に人を斬ってるから、それでいろんなものや力もつけているからね。その部分を見ても、簡単ではないかなあと思ってるわ
降霊専門の人、そのあとに不要物を恵子さんが殴って追い出す、そして陽子さんが仕上げる、とかのほうがいいんじゃないですかね?
それもありねえ。このくっついてるのも頑丈だから私が降霊で誰か剥がす人でもいいんだけども
しかし、立派ですよねえ。私も模造刀で一つ欲しいなあとは思ってるんですが。観賞用に
買ったら持ってきてくれたらへんなものが入らないようにしてあげるわよ。普段色々してもらってるから
形がね。刀ってもの自体が引き寄せやすい部分もあるし、人形と同じようなものだと思ってもらえれば
そうねえ。安全にやってもらったほうがいいわよ?購入するのなら
もう一人声をかけて、明日改めて一日で終わらせちゃいましょうか
そうですねえ。この子(刀)も早く良い状態に戻りたいでしょうし
三人目のイタコさん

翌日、再度恵子さんのお家にお邪魔しました。
恵子さんと陽子さん、そして三人目のイタコさんになるSさんがそこにいました。
(Sさんの希望で今回はお名前をSさんにさせていただきます)
Sさんは非常にお若い方で、幼少期から霊的なものに触れる生活だったらしく、修行を積まれて若いうちから活動を始められたそうです。
恵子さんの住む場所からは1時間ほど離れたところに住んでらっしゃる方ですが、普段は農業をしながら霊的な対応ができるようにしているそうです。
見学させていただきますKです。よろしくお願いします~
Sさんはとても気さくな方で、芸能人でいうところの天海祐希さんに似ていると感じました。
わたしとSさんが対面している間に陽子さんが刀の周りに様々な道具を配置していき、今からこの刀の降霊が始まるのだと思うといろいろな気持ちがよぎります。
今回は恵子さんが降霊、Sさんが除霊、陽子さんが縁の固定という担当のようです。
恵子さんが刀に向かって榊を振り下ろすと、小皿の上の塩がどんどん変色していきます。
その塩を恵子さんの目線の合図で交換する役目をさせてもらっているので、死の変化が速いことにも驚きました。
バシバシと何度も恵子さんが榊を振り下ろすたびに交換した塩が腐っていきます。
その塩を小箱に移動させ、新しい塩を何度か入れていたころ恵子さんがこちらを振り向きました。
一先ず、おろせたけどもどうしましょう?話し合いをする気はないみたい。ただ、足利が同タラとか言ってるからその辺の時代みたいね
ついでにどの足利なのか聞いてみてください。足利さんいっぱいいますので
ですね。あと、オダノブっていう人が久々にいてちょっと嬉しいです
Sさんからみて今おりてきてる人はどんな感じの人ですか?
武士じゃなく武将じゃなく、当時の傭兵集団の僧侶な感じがするのよねえ。坊主じゃなくて本当に侍の前の原型になるあの集団
だと、有名なものというよりもちょうど量産されたあたりと考えると、オダノブの手前あたりですかね
あのへんのだと雇用主は全部足利さんに行きつくからね
その辺みたいね。この人が目的としたのは自分の死ぬ前に家を守るために奉納したっぽいんだけども
人斬ってるものをそのまま奉納してもいいことないですからねえ
それが数百年たってこうなってるのね。本人もできるなら自分がこの刀の守護になりたいという考えはあるみたいよ
だと、絡まってるのを全部吹っ飛ばしますか?それだとこの人も吹っ飛びそうな気もしますが
結構弱ってるからねえ。一つずつ吹っ飛ばしてもらっていく感じでお願いできる?
了解です。だと、今おろされてる人にはできるだけ安全な場所まで潜ってもらえるようにお願いできますか?あと恵子さんも念のためにその人に防護張ってもらえれば。私、まだ完全にコントロールできないんですよね(笑)火力強めというか
Sさんのやり方とは?

恵子さんと後退したSさんが今度は刀の鞘や装具を触り、ゆくっりと刀身を抜きました。
Sさんは自分の髪の毛を一本抜いてその刀身にあてて、刀身に絡まっているという何かをはがしていくことになりました。
筆者にはその光景は見えませんが、一体ずつ丁寧に剥がしていき、そのたびに恵子さんのいうところの「笑顔で往復びんたをしている。何回も」という状態だったようです。
刀身に変化はありませんが、Sさんは明確に疲労が蓄積しているのが見えました。
汗が落ち始め、最初にSさんが刀身にあてた髪の毛がなぜかかすかに動いているように見えました。
もう少ししたら変化が出るから楽しみに待ってるといいわよ
それから間もなく、室内に大音量の鈴を鳴らす音が響き始めました。
この室内にそんな大きな音を出すものはなく、鈴がここまで大きなものになるとすればそれは神社などにあるあの大きさのものになります。
そんなものを鳴らしたりぶつけたりする音が、がんがんと響いており今自分がいる状態が普通ではないことを再確認することになりました。
私にもはっきりとわからなくてね。一気にやっちゃうと刀本体まで行っちゃうくらいにはいろいろとくっついてるのよ。時間がたちすぎてるから悪いものものそれなりにね
Sさんに失礼になるからね。あれだけの力があるんだから大丈夫よ
陽子さんは小さな鈴を取り出してゆっくりと揺らしていきます。
本来の鈴の音がするたびに騒音ともいえる鈴の音は消されて行きました。
この程度で脅しになると考えてるのがくっついててよかったですねえ
あらやだ。陽子さんがそんなもの使ったら逆におどしになるでしょ(笑)
Sさんと何かの除霊合戦は1時間ほど続きました。
ぐったりとしたSさんと陽子さんが交代しSさんが私の隣に座りました。
なんというか、当時の政権交代みたいなものとかかなあ……でもこれは仕方のないものなのかもしれないけども、そのあとも結構いろんなところを流れてるというか。奉納したものの当時結構高価なものだから盗まれてあちこち転々としてるうちにいろんなものをくっつけちゃったというか。猫がどっかでかけていろんなものくっつけてるというか
中には子供を斬ってるのもあったからその辺も大きいのかなあ。そのあたりは先輩方にお任せしてしまうのが一番だと思うんだけどもね
こんなのを顔色も変えずにできるあの二人はすごいなあ
ペットボトルの水を飲みながらSさんは陽子さんの背中を見つめていました。
完全分業にすることでそれぞれが最大の能力を出せるという部分が今回は採用された形です。
刀もですが刃物は人が触れることで様々なものを引き寄せやすいこともあるようで、模造刀やオーダーメイドのはさみなどでも同じだということでした。
恵子さん、このお坊様、といっていいのかしら?この方をこの刀の守護として固定していいのかしら?
それでお願いしますね。その人が元々はそれを希望しているはずなので
では、そのあとに購入した〇さんの家の守護になることを伝えてよろしいですか?
陽子さんが懐紙で何度か刀身を撫でていくと室内の空気が変わっていくのがわかりました。
じっとりとした空気が消え、いつもの恵子さんの自宅の一室になっているのを感じます。
霊的なものは一切持っていなくともわかるほどです。
なんとかこちらのことは理解してくれて、守護刀になることも了承してくれたわ。〇さんのおうち、男の子いるでしょ?その子の守り刀になるみたいね
問題ないですよ。縁のほうも何とかなりましたし、しばらくはこのいい状態も続く。今後手入れや人が触れ、子供さんの精気に触れることで本来の人格を取り戻すでしょうし
物語の意外な終わり

それから数日して、刀は依頼した方のもとに戻ったそうです。
ですが、このお話には意外な終わりが付いていました。
まあねえ。一応は終わったんだけども、〇さんの家のお子さんってまだすごく小さいんだけども……
もう一つの希望がなんというか、一度でいいから元のというか、最初の持ち主の土地に戻りたいといういうか……結構離れてるというかね
うーん、なんというかね……その土地を守ってるというか、戻りたい土地にいる存在、本家というべき存在になるのかしらねえ……たぶん、その当代になる子が女の子なのよ
なんというか、下手に力を戻しちゃったからもしかしたらその二人が将来的に一緒になる可能性を作ってしまったかもというかね……もちろんそうならないこともおおいけども、縁もゆかりもない二人で全く住む場所も違う二人がそういうものができてしまったかもと思うと、ちょっと申し訳なく思うというか
それまではいろいろと時世も変わるだろうけども、大学とかで無理やりあの刀が動かないようにするべきだったかなあと思うのよね
そういう、ものに宿る何かがきっかけで一緒になるとかもあるんですか?
あるわよ。結婚することで元の場所に戻れるとなれば何代かかけて移動していく根性のある呪物とかもあるし。大体はいいものであっていい結果になることが多いけど、中には片方は気持ちがあっても、もう片方はそうじゃないとかになるとちょっと大変なのよね
陽子さんも少しそれを心配してたのよね。ちょっと力を戻しすぎたかもしれない、と。あの人はその辺すごくしっかりとした仕事をする人だからあの人の縁結びの効果があるうちはそこまで自由にはならないだろうけども、何事も期限があるからねえ……そのときに落ち着いてくれてるといいんだけどもね。そこまでは私たちの管轄外にはなるんだけども……あの時代の人は気持ちが強いからねえ……
〇さん、購入した依頼者の家で丁寧に祀られてるわ。だから力もつきやすいってのあるんだけども……まあ、これはなんともねえ……いいカップルになるといいんだけども。陽子さんの縁結びの残り香を使って無理やり二人の縁を結んでしまう可能性もないとは言い切れないからねえ
まあ、まだね。どちらも幼稚園だけども二人が16とかになったあたりから変化が出てきそうなのよね
いいほうに考えれば運命の出会いになるけれども、悪くすれば自分たちの意思を無視した出会いになる。それこそ、戦国時代の許嫁みたいな存在ね。そこにお互いの意思が介入できないものであり、出会ってからどこまで愛をうむことができるか。まあ、その時代の刀で元が僧侶ならしかたないのかもしれないけどもねえ……ちゃんと祓って違うもの入れておくべきだったかなと思わないこともないのよ
刀っていうのはあんまりないわね。除霊中にケガする可能性とかもあるから、それなりに実績ある人の処に持ち込まれるというか
刃物関係は嫌だって言ってる人も多いからね。私はその辺はそれなりに慣れてるけども、いきなり刀から何かが飛んでくると本体は目の前にあってもメンタル的にね
なんにでも宿ることはあるけども、金属のものが圧倒的に多いわね。海外だとアクセサリー、日本なら刃物やかんざしね。あとはべっ甲とか鹿の骨とかを使ったものも生命を経由しているからそういうのも宿りやいわね
石やサンゴは形成される段階で入れる隙間があるかどうかもだけども、人が加工して人に触れるものとかは宿りやすいわね。人っていうのはそれだけ特殊なんでしょうね
アンティークは素敵だけど、気を付けないといけないですね
そこまで極端なものとかはあんまりないんだけどもね。この巣ごもりで寄せ合ってしまって相性のいい人のところにそういう呪物になったものが届いてしまうこともあるのよね
家にいるとネットに触れる時間も増えちゃいますからね
しばらくはこういう情勢だろうし、気を付けていきたいわね
ですねえ。私もリサイクルショップでかんざしとか買っちゃうので気を付けないと
大丈夫。あなたになにかあったらすぐに何とかできるから
何もないほうが希望です。今日はありがとうございました
霊能者体験談
さらに霊能者の体験談を見たい方は下記をクリック!